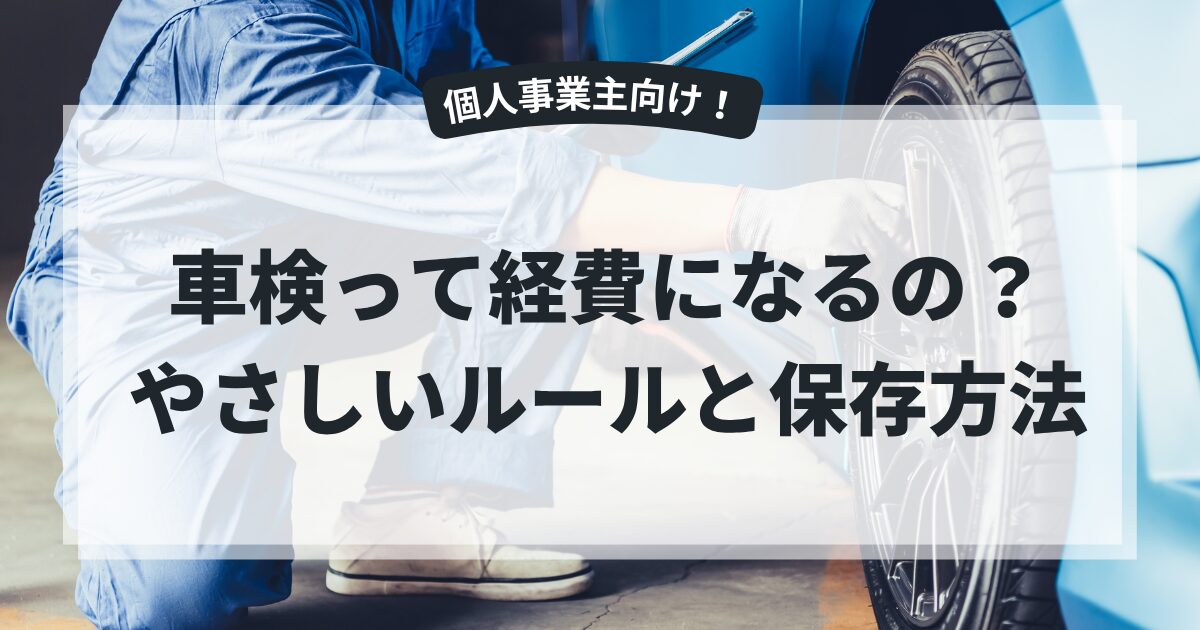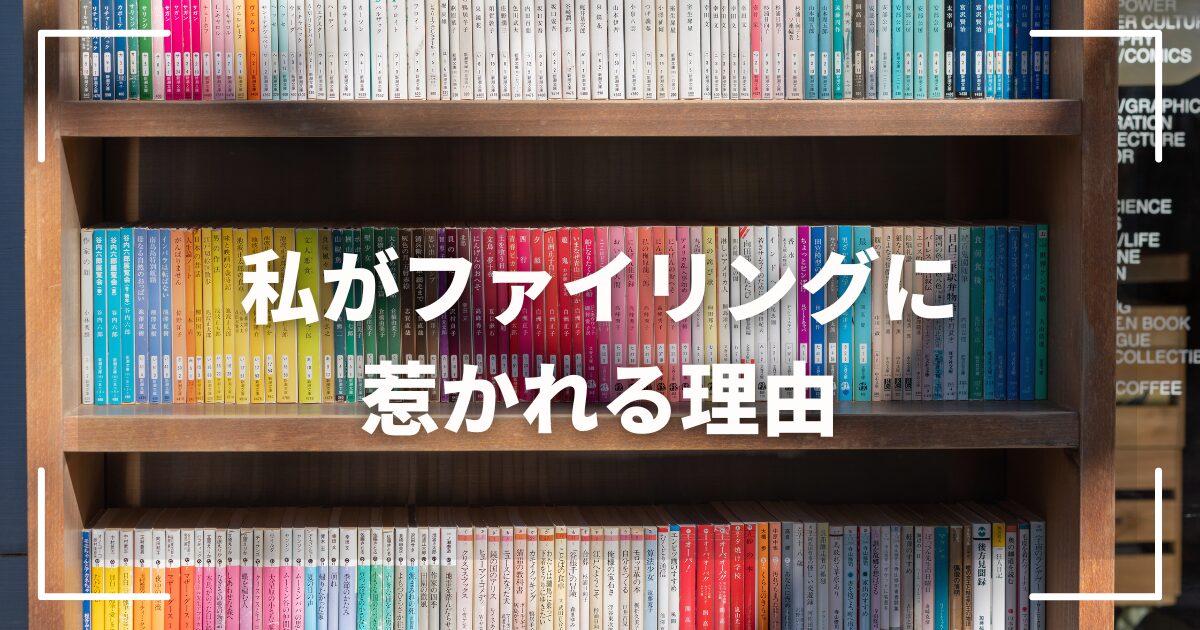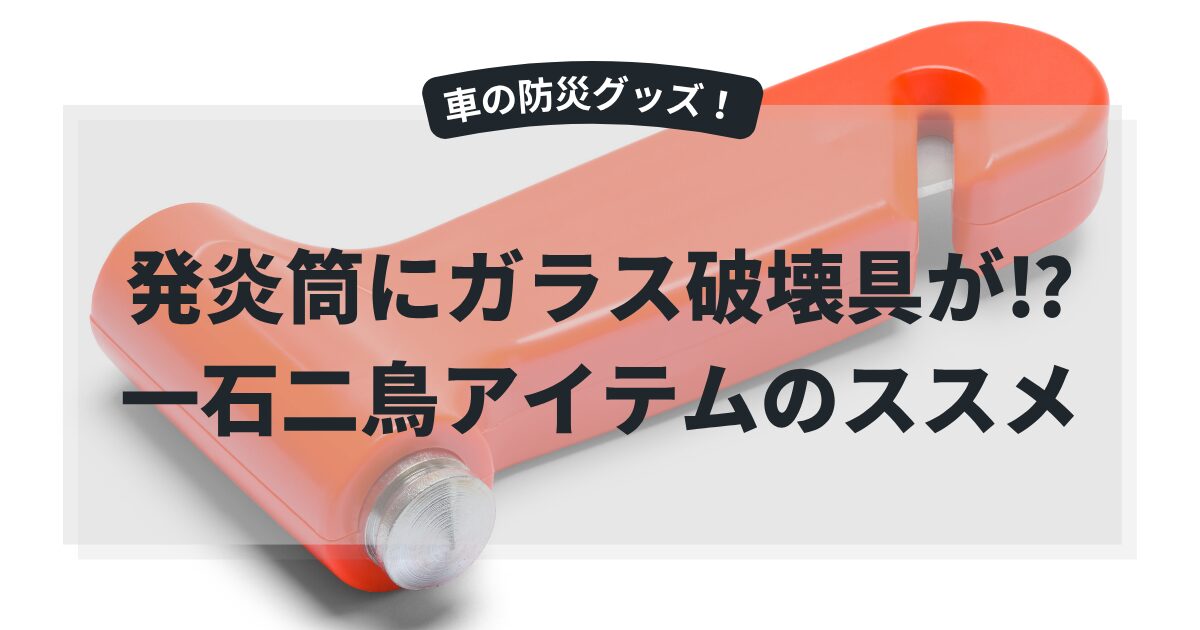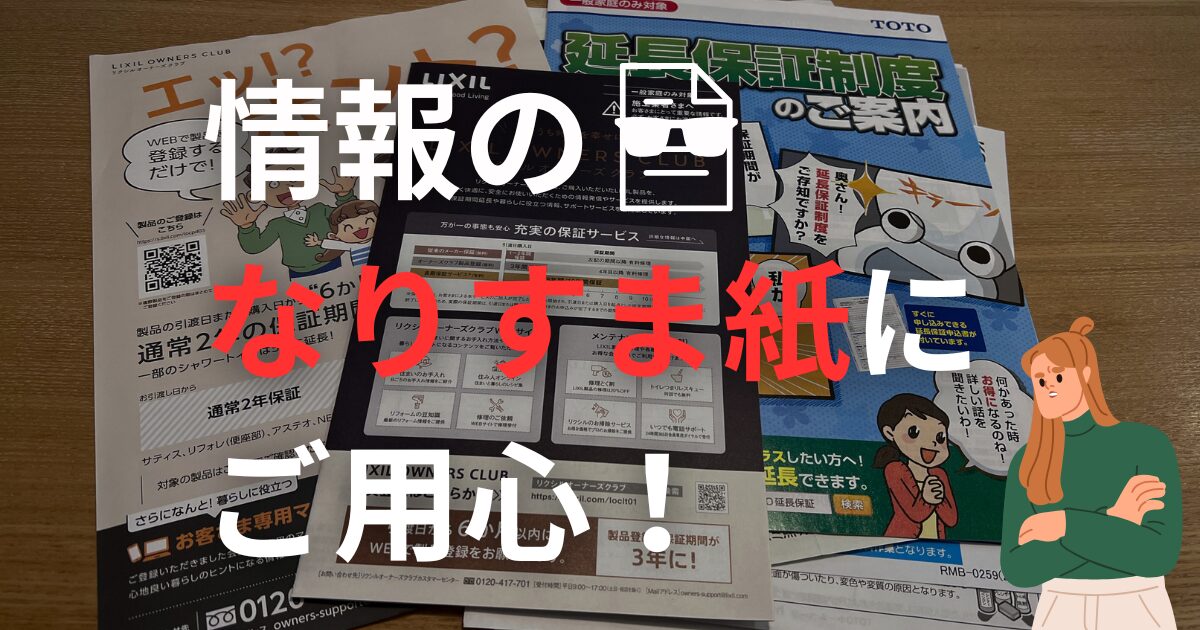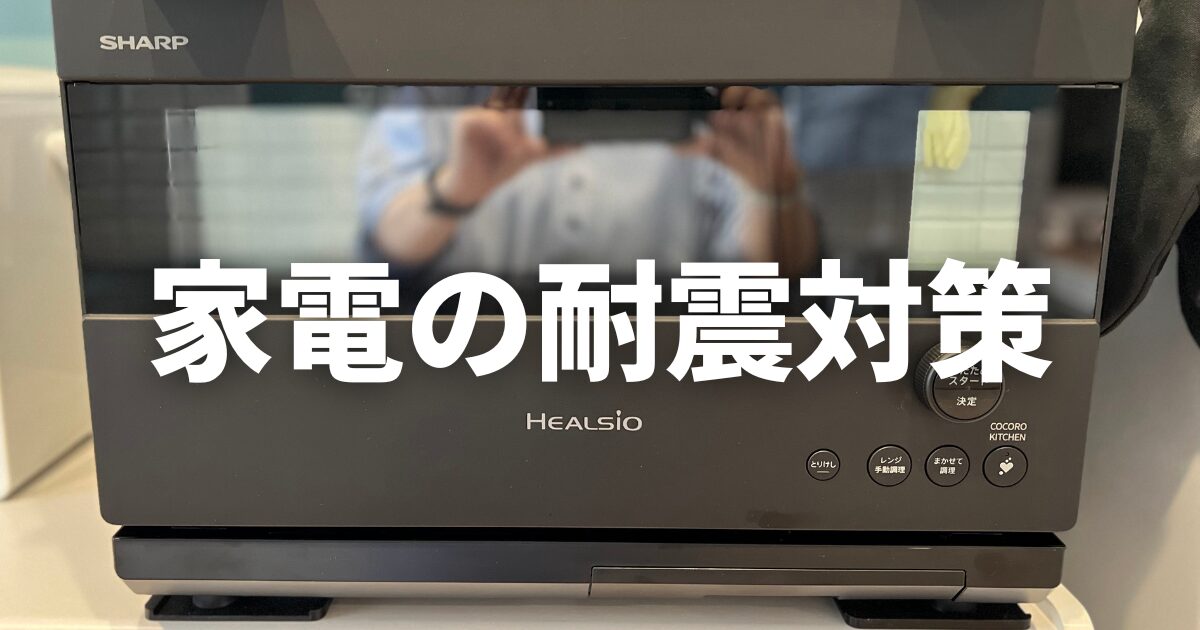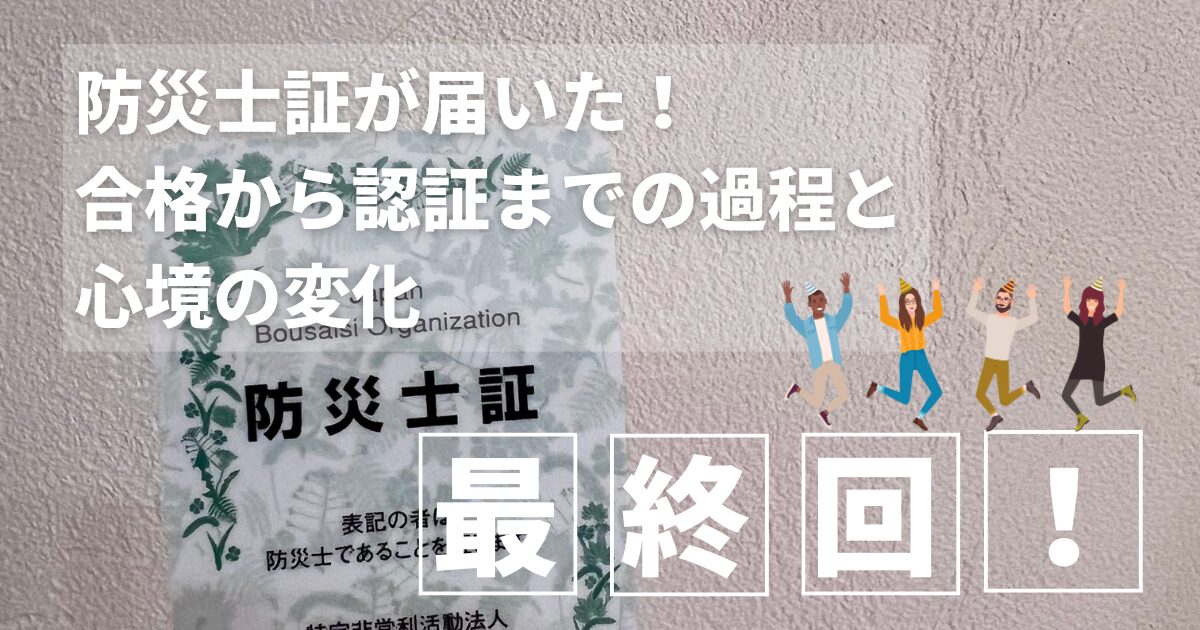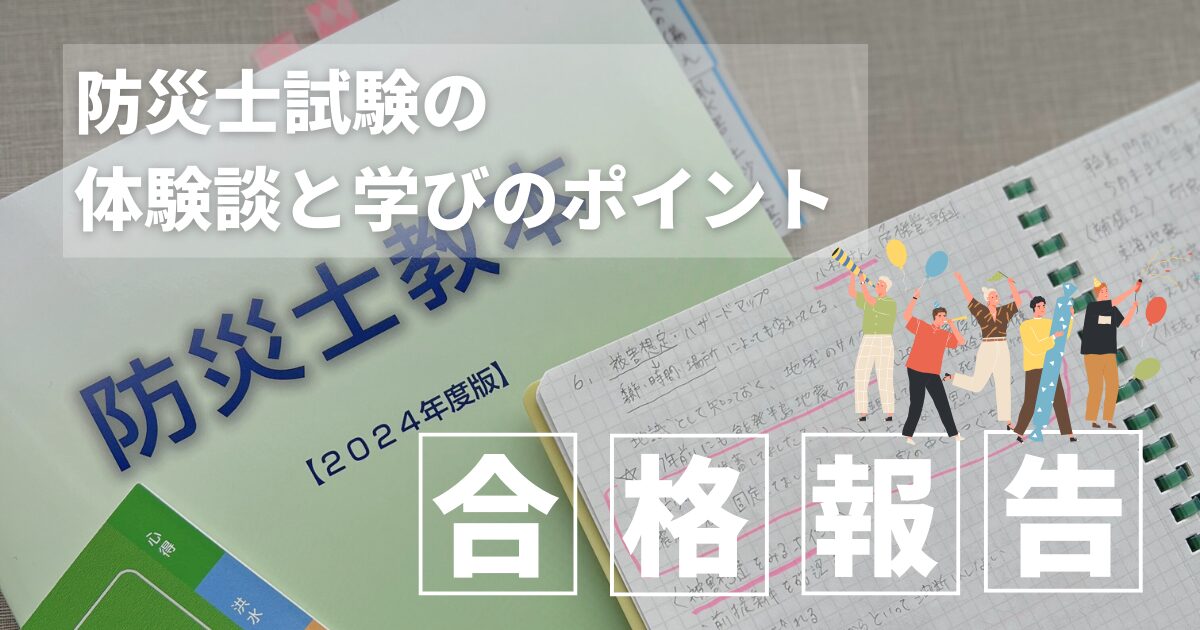はじめに
車検の請求書を見て、「これって経費にできるのかな?」と迷ったことはありませんか?
車検は2〜3年に1回のことなので、毎回「どうしてたっけ?」と悩みがちです。
私自身も今回あれこれ迷ったので、備忘録も兼ねて、個人事業主さん向けに、やさしく・わかりやすくまとめてみました。
車検費用は経費にできる?
個人事業主の方が車を事業に使っている場合、車検費用も経費にすることができます。
ただし、プライベートでも使っている場合は「家事按分(かじあんぶん)」が必要です。
たとえば10万円の車検費用がかかって、普段の使用割合が“仕事6割・プライベート4割”なら、6万円分だけを経費として計上するイメージです。
車検費用の内訳と勘定科目
車検費用は大きく2つに分かれます。
| 項目 | 内容例 | 勘定科目 |
|---|---|---|
| 法定費用 | 自動車重量税・自賠責保険・印紙代 | 租税公課・保険料 |
| 点検・整備費用 | 車検基本料・整備費・手数料 | 車両費・修繕費・支払手数料 |
車検費用は項目ごとに分けて記帳する必要があるため、明細があるとスムーズです。
経費処理で必要な書類
| 書類 | 保存の必要性 | 例・補足 |
|---|---|---|
| 請求書 | 必須 | 経費の金額・取引内容の証明に |
| クレジットカード明細 | 推奨 | 実際の支払い証明として |
| 納品書 | 任意 | 記録用には便利だけど必須ではない |
| 領収書(もらえるなら) | 推奨 | 支払証明になる。請求書とあわせておくと安心 |
私の迷わない保存ルール
- 紙でもらったものは紙で保存
- データでもらったものはデータで保存
→ ルールを決めておくことで迷わずスムーズ。
2024年以降は、メールやWebで受け取った請求書や領収書などの電子データは、「電子帳簿保存法」により電子のまま保存が義務化されています。紙に印刷しただけでは要件を満たさない場合があるのでご注意ください。
クラウド会計アプリに保存する方法も検討したのですが、保存期間とアプリの継続利用を考慮した結果、今のような方法が自分にとってラクだなと感じています。大切なのは「必要な書類の住所が決まっていること」です。
スポンサーリンク
保存期間は何年?(青色申告の個人事業主の場合)
| 書類の種類 | 保存期間(個人事業主) | 根拠 |
|---|---|---|
| 請求書・領収書・契約書など | 7年間(基本) | 所得税法・帳簿保存義務 |
| クレカ明細 | 7年間が望ましい | 支払証明の補足資料として |
| 納品書 | 任意 | 補足用なので自由 |
例えば、請求書は「事業用のフォルダ」、納品書は「家庭のフォルダ」に分けて残しておく、という方法もアリです。
どの書類を残すか、どこにしまうかは、「自分や家族があとで迷わないこと」をいちばんに考えると良いです。
ちなみに私は、見積書と納品書の内容がほぼ同じだったので、見積書は処分して納品書だけ残しました。
「内容が重複しているなら、どちらかを残せばOK」と決めておくと、迷わずスッキリ保管できます。
忘れがちな処理をラクにする方法
「どうしてたっけ?」が起きる原因は、記録がない or ルールがないから。
例えば、
- 「経費処理メモ」をメモアプリに記録
- 家事按分の内訳や根拠もアプリ内に記録
決まりを1回作っておけば、未来の自分が助かります。
仕訳例:車検費用の経理処理イメージ
【例】
・法定費用:24,140円(重量税印紙代5,000円+自賠責保険17,540円+検査手数料等1,600円)
・部品代:17,908円
・車検基本料:50,000円
・事業使用割合:60%
・支払い方法:個人のクレジットカード
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 租税公課 | 3,960円 | 事業主借 | 55,229円 | 車検費用(60%按分) |
| 保険料 | 10,524円 | 自賠責保険(60%按分) | ||
| 修繕費 | 10,745円 | 車検整備費用(60%按分) | ||
| 車両費 | 30,000円 | 点検費用(60%按分) |
おわりに
今回ご紹介したのはあくまで一例。
でも、「紙なら紙」「データならデータ」と決めるだけで本当にラクになります。
迷いやすい人こそ、自分なりの“ざっくりで続くルール”を見つけてほしいです。
「こうやっておけば大丈夫だったな」と思える自分なりの型ができると、日々の経理や書類整理もずっとラクになります。
もしこの記事が、同じように迷っている誰かの役に立てばうれしいです。
一緒に“迷わない仕組み”をつくっていきましょう!
注意事項
本記事は、売上1,000万円以下の免税事業者を対象とし、筆者の経験や一般的な情報をもとにまとめています。
免税事業者の場合、消費税の納税義務やインボイス制度(適格請求書発行事業者)への対応は原則として必要ありませんが、事業の状況や法令の改正等により対応が異なる場合があります。
実際の経理処理や税務申告、請求書の発行については、最新の法令や公的機関の情報(国税庁「消費税のしくみ」 など)をご確認いただくか、税理士等の専門家にご相談ください。
スポンサーリンク